中国の野望を砕く快勝劇。
1月9日にアジアカップが開幕する。連覇を目指す日本は12日のパレスチナ戦で大会をスタートさせる。
史上最多4度のアジア制覇を成し遂げている日本代表。ドラマに富んだその4度の優勝を『週刊サッカーダイジェスト』のアーカイブからお届けしよう。
“完全アウェー”の中国で連覇を達成したのが、2004年大会のジーコジャパン。頂点には立ったものの、選手の自主性に任せたジーコの指揮には危うさが見え隠れした。
特派レポートを週刊サッカーダイジェスト2004年8月24日号より。
――◆――◆――
中村のスルーパスが中国のディフェンスラインを切り裂いたとき、日本の連覇はほぼ確定した。ボールを受けた玉田を追う中国DFに覇気はなく、戦意も喪失、ゴールの中に転がるボールを眺め、早くリスタートしようという意思さえ感じられなかった。
3-1。決勝戦としては申し分のないスコア、そして圧巻のチームパフォーマンス。耳をつんざくような声援が響く工人体育場のピッチで、日本は中国の誇りと野望を粉砕し、見事、連覇の偉業を成し遂げたのである。
田嶋幸三・技術委員長はこう総括する。
「たしかに戦術上で課題とすべき点は少なくなかったが、ジーコイズムというか、メンタルのところでタフに戦う姿勢が、スタメンだけでなくサブを含めたチーム全体に浸透してきた。そのなかで遂げた今回の優勝というものは、非常に大きな意味を持つ」
正直、大会の初戦となったオマーン戦を終えたとき、このチームが決勝戦に到達するのは極めて難しいだろうと予測していた。その後も負けはしないものの内容で圧倒され、ヨルダン戦に至っては、多分に運が味方した感さえあった。
だが、この日の日本が見せた組織としての質は、今大会でどのチームが見せたそれよりも上を行っていた。人とボールが絶え間なく動き、気候と自身のスタミナとを計算しながら、最大限のチャレンジで相手にプレッシャーをかけていく。常にゴールを意図した攻撃的な姿勢があり、チームはまるでひとつの生き物のようであった。
立ち上がりこそ中国の勢いに押される場面もあったが、かつてないほどの高いライン設定を試み、無意味な横パスは極力避けて、相手の焦りを誘う。中国はしびれをきらして勝負のパス、シュートを繰り出すが精度は伴っていない。
宮本が「相手のトップのひとりがトップ下の位置に下がっていたのを抑えてからは、日本のリズムになった」と語るように、ターゲットを確実に潰してパスコースを限定させ、サイドに追い込み、複数の人間がプレスに関与していく理想的な守備が形成されていた。練習の大半を割いていたセットプレーから先制、10分後にはいったんは同点とされるが、危機に陥ればファウルで止めにかかるなど、試合巧者ぶりものぞかせた。
後半になると中国はラインを無闇に上げることはなくなったが、これを見て日本は選手間のポジションチェンジを頻繁に行ない、さらにプレスのポイントを高く設定した。CKから今大会初先発の中田浩が勝ち越し弾を決め、相手の矢継ぎ早の交代に混乱する場面もあったが耐え凌ぎ、最後は玉田が試合を決定づけた。選手たちの頼もしさに、感服するばかりだった。
変われば、変わるものだ。この3週間で刻んだ苦闘の記憶と連覇への重圧を、選手たちは最高の形で昇華させてしまった。これがジーコジャパンであったから実現できた、という意見に反論はしない。自由にして、一体感のある雰囲気が根底にあったからこそ、日本は戴冠の瞬間を迎えることができたのだから。
溜りに溜っていた鬱憤を一気に放出したのは、準決勝のバーレーン戦、その2日前のことである。この「地殻変動」が、ジーコジャパンを新たな次元へと誘ったのである。
史上最多4度のアジア制覇を成し遂げている日本代表。ドラマに富んだその4度の優勝を『週刊サッカーダイジェスト』のアーカイブからお届けしよう。
“完全アウェー”の中国で連覇を達成したのが、2004年大会のジーコジャパン。頂点には立ったものの、選手の自主性に任せたジーコの指揮には危うさが見え隠れした。
特派レポートを週刊サッカーダイジェスト2004年8月24日号より。
――◆――◆――
中村のスルーパスが中国のディフェンスラインを切り裂いたとき、日本の連覇はほぼ確定した。ボールを受けた玉田を追う中国DFに覇気はなく、戦意も喪失、ゴールの中に転がるボールを眺め、早くリスタートしようという意思さえ感じられなかった。
3-1。決勝戦としては申し分のないスコア、そして圧巻のチームパフォーマンス。耳をつんざくような声援が響く工人体育場のピッチで、日本は中国の誇りと野望を粉砕し、見事、連覇の偉業を成し遂げたのである。
田嶋幸三・技術委員長はこう総括する。
「たしかに戦術上で課題とすべき点は少なくなかったが、ジーコイズムというか、メンタルのところでタフに戦う姿勢が、スタメンだけでなくサブを含めたチーム全体に浸透してきた。そのなかで遂げた今回の優勝というものは、非常に大きな意味を持つ」
正直、大会の初戦となったオマーン戦を終えたとき、このチームが決勝戦に到達するのは極めて難しいだろうと予測していた。その後も負けはしないものの内容で圧倒され、ヨルダン戦に至っては、多分に運が味方した感さえあった。
だが、この日の日本が見せた組織としての質は、今大会でどのチームが見せたそれよりも上を行っていた。人とボールが絶え間なく動き、気候と自身のスタミナとを計算しながら、最大限のチャレンジで相手にプレッシャーをかけていく。常にゴールを意図した攻撃的な姿勢があり、チームはまるでひとつの生き物のようであった。
立ち上がりこそ中国の勢いに押される場面もあったが、かつてないほどの高いライン設定を試み、無意味な横パスは極力避けて、相手の焦りを誘う。中国はしびれをきらして勝負のパス、シュートを繰り出すが精度は伴っていない。
宮本が「相手のトップのひとりがトップ下の位置に下がっていたのを抑えてからは、日本のリズムになった」と語るように、ターゲットを確実に潰してパスコースを限定させ、サイドに追い込み、複数の人間がプレスに関与していく理想的な守備が形成されていた。練習の大半を割いていたセットプレーから先制、10分後にはいったんは同点とされるが、危機に陥ればファウルで止めにかかるなど、試合巧者ぶりものぞかせた。
後半になると中国はラインを無闇に上げることはなくなったが、これを見て日本は選手間のポジションチェンジを頻繁に行ない、さらにプレスのポイントを高く設定した。CKから今大会初先発の中田浩が勝ち越し弾を決め、相手の矢継ぎ早の交代に混乱する場面もあったが耐え凌ぎ、最後は玉田が試合を決定づけた。選手たちの頼もしさに、感服するばかりだった。
変われば、変わるものだ。この3週間で刻んだ苦闘の記憶と連覇への重圧を、選手たちは最高の形で昇華させてしまった。これがジーコジャパンであったから実現できた、という意見に反論はしない。自由にして、一体感のある雰囲気が根底にあったからこそ、日本は戴冠の瞬間を迎えることができたのだから。
溜りに溜っていた鬱憤を一気に放出したのは、準決勝のバーレーン戦、その2日前のことである。この「地殻変動」が、ジーコジャパンを新たな次元へと誘ったのである。













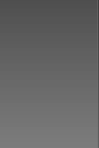
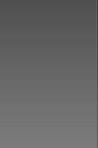














 定価:1650円(税込)
定価:1650円(税込) 定価:980円(税込)
定価:980円(税込) 定価:980円(税込)
定価:980円(税込) 定価:1100円(税込)
定価:1100円(税込)
